企画展示
「先生方のおすすめの本を知りたい!」という多くの学生の皆さんからのリクエストにお応えし、シリーズ企画展示「先生の推し本」としてお茶大の先生方おすすめの本を紹介しています。
先生方には、次の3つのテーマから1つ選択して、推薦いただきました。
① 専門からの推薦図書(専門領域の基本文献、その分野に進まれるきっかけとなった図書など)
② 個人的な興味・関心からの推薦図書
(読後の印象がよかったもの、思い出に残っているもの、趣味・個人的関心に関係する図書など)
③ お茶大生に読んでほしい本(専門にかかわらず、大学生にぜひ読んでほしい推薦図書)
推薦いただいた本のリストと先生方からのコメントは、こちらのページで見ることができるほか、図書館1階スカイグローバルラーニングコモンズには実物を展示しています。
展示している本は、手に取ってご利用になれるほか、貸出も可能です
(一部貸出不可のものもあります)。
ご来館の際はぜひお立ち寄りください。
第6回 浅本紀子先生(理学部情報科学科)
2022年12月12日~2023年3月10日
テーマ 私の思い出本
~大学入学してから節目の時にあった本たち~
<テーマ選択②>
思い出に残っているものということで、自分が大学生になったころから思い出しながら徒然と挙げていたら、とりとめのないリストになりました。 現代の大学生の皆様向けでない本も混ざっていますが、当時の自分の思い出本です。 小さい頃から本を読むのは好きな方で、大学入学で上京してからは自分で買う本は文庫や新書になりましたが、それでも場所を取るので下宿の頃は本棚や押し入れからはみ出した本の山に困ったものです。 数年前に意を決して中身を見ずに紙の本の山を処分して、現在は主に電子書籍です。 紙の本の良さが捨て難かったですが、物理的制約を気にせずに保有できて色々な場所で読めるメリットは抜け出せなくなりました。昔の本も随分と電子版で復刻されており便利になったものです。 デメリットといえば、ワンクリックで買えてしまいついつい散財してしまうことでしょうか…。皆さんは、ぜひ図書館を活用の上、ご利用は計画的に!
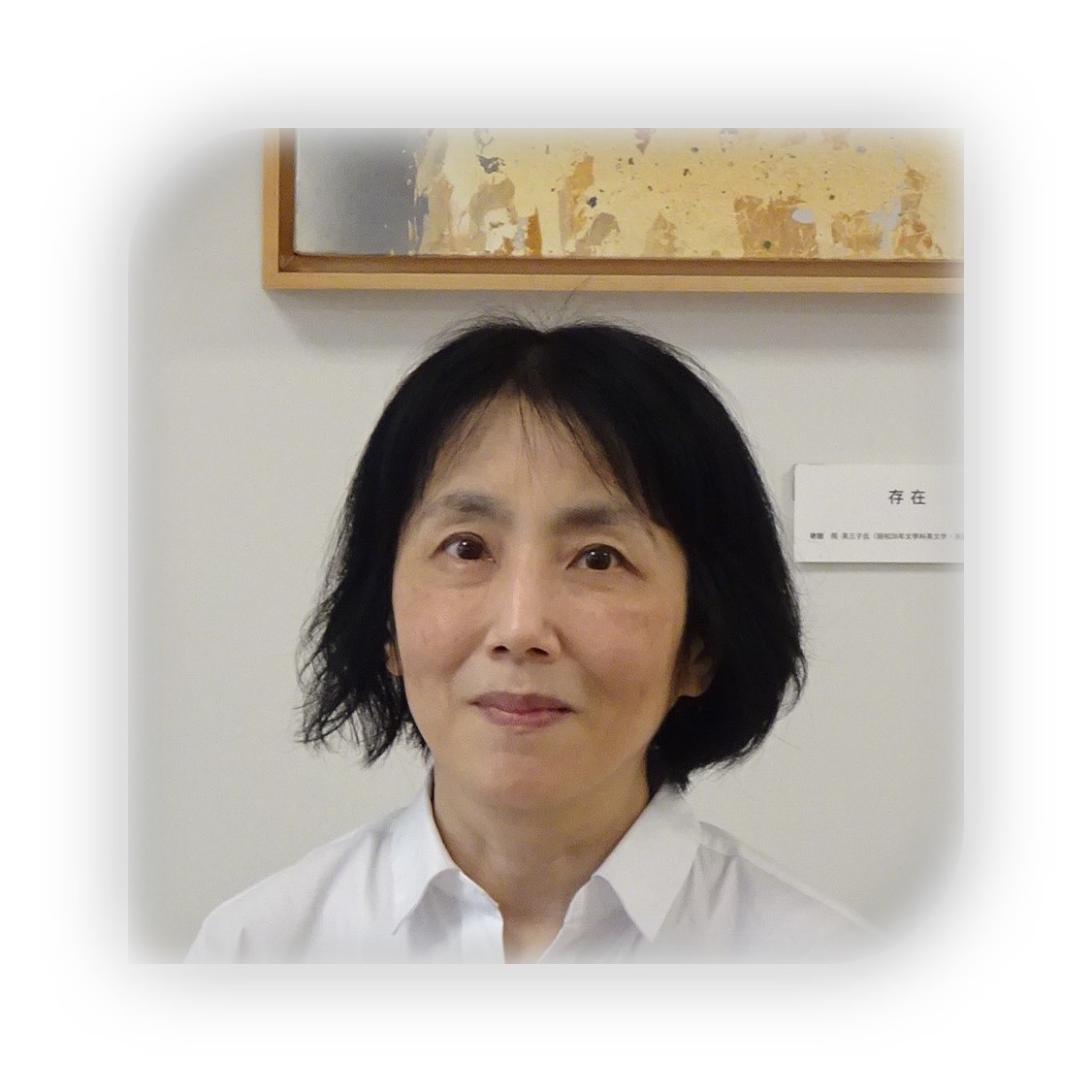
1983年、お茶の水女子大学理学部数学科を卒業。1985年、お茶の水女子大学大学院理学研究科修士課程数学専攻修了。博士(工学)(1998年 信州大学)。
株式会社日本サイバネテクス、お茶の水女子大学理学部助手、同理学部助教授、同情報基盤センター長などを経て、現在お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系教授。
専門は、計算機支援、学習管理システム、情報教育。
浅本先生の推し本 一覧(2022/12/12更新)
| 書名 / 著者等. (出版社, 刊行年月. シリーズ名) |
配架場所 請求記号 |
先生からのコメント |
| カッコウはコンピュータに卵を産む / クリフォード・ストール著 ; 池央耿訳 (草思社, 1991.9) | 図書館オープン書庫(一般図書) 936/St7/1-2 |
かなり古い本ですが、当時大学に就職して間もないころ、自分がまだ外部ネットワークに繋がるサーバーなどに縁がなかったころに読みました。実際に起こった世界的ハッカー事件の全容を当事者本人が忠実に記録したノンフィクションです。実話なのが信じられないほどのエキサイティングな展開で、ワクワクドキドキしながら一気に読みました。ネットワークやUNIX等の知識がなくても面白く読めると思います。30年以上前に読んだその後、自分が大学のシステムやネットワークに関わる機会があり出くわしたサイバー事件は、この1キロ分の1くらいの規模ですかね。 |
| ガードナーの数学パズル・ゲーム : フレクサゴン/確率パラドックス/ポリオミノ / マーティン・ガードナー著 ; 岩沢宏和訳 (日本評論社, 2015.4) | 図書館一般図書 410.7/G22/1 |
高校生大学生の頃、ガードナーに代表される数学パズルの本が好きで、色々借りて(若い頃は文庫や新書以外の本は金額的に買いにくかったので)読んでいました。最近MGの完全版の全集が出ていたので、発刊済みの4冊を購入してチビチビと章のつまみ食いで楽しんでいます。学生の当時は500円を超える本はサイフの事情で買いませんでしたが、今では積ん読用に大人買いしているのは感慨深いですね。 |
| プログラミング言語C : ANSI規格準拠 / B.W. カーニハン, D.M. リッチー著 ; 石田晴久訳 (共立出版, 1994.3) | 図書館オープン書庫(一般図書) 548.964/Ke57k |
大学院を出た後くらいの若いころに(初版を)読んだ本です。当時、民間でパソコンといえばNECのPC-9801で、プログラムはBASICかアセンブラ、プリンターはドットインパクトという時代でした。趣味やバイトで本体同梱のマニュアルや雑誌記事の見よう見まねでプログラムを書いていたので、この本が私が初めて読んだプログラミング言語の本です。開発環境がなかったので、先頭から末尾まで本だけで読み通しました。それでも初めての世界だったので興味深く読んだ思い出の本です。今ではちょっとやりたくないですし、学生のみなさんに読んだ方がよい本とは言いません。余談ですが、茗荷谷駅横の今サイゼリヤが入っている共立ビルは、K&R本の売上で立てたという都市伝説があるくらいのベストセラーな本です。 |
| 集合論入門 / 赤攝也著 (筑摩書房, 2014.3) | 図書館文庫・新書 415/Se24 |
大学1年生の前期の授業の教科書の一つでした。高校までの数学の教科書とは違った雰囲気の著者の言葉で綴られた、古典的集合論の入門書です。大学入学して初めて受けた数学の授業で、大学では必ずしも先生が教科書に指定した本に沿った授業をするのではないのだなというのを知らされました(用語や記号の使い方など)。これから大学でこんな数学を学ぶのだなと思いながら、紙と鉛筆を片手に読んでいった思い出の本です。 |
| 若き数学者のアメリカ / 藤原正彦著 (新潮社, 1977.11) | 図書館オープン書庫(一般図書) 295/F68 |
「国家の品格」で知られる藤原正彦先生のアメリカ留学記です。著者の若さが感じられる文章で、すっと読めます。藤原先生は、私の入学当時数学科で一番若い助教授で、すでに日本エッセイスト・クラブ賞などで有名な方でした。思い出として、修士の授業で当時翻訳に関わっていらした「月の魔力」がらみで、授業とは全然違う内容の、出産数と月と地球の周期の関係の数学の話で1週分の講義がありました。 |
| 無限と連続 : 現代数学の展望 / 遠山啓著 (岩波書店, 1952.5. 岩波新書 ; 青版-96) | 図書館文庫・新書 410/To79 |
著者は数学教育の分野でもよく知られており、多くの数学エッセイも執筆しています。本書は、無限を数えることで始まり集合や群について説明されていく数学の啓蒙書です。 今は電子書籍が便利ですが、私が大学生の頃は、当たり前ですが全ての本は紙で売られていました。当時、最寄駅から下宿に帰る道の途中に本屋があり、そこで毎週のようにブルーバックスや新書の理系本を買って帰って読んでいましたが、これはその頃読んだ一冊です。 |
| The art of computer programming / D.E. Knuth著 (サイエンス社, 1978-1986) | 図書館オープン書庫(一般図書) 548.964/Kn8/1-4 |
TeXで知られるクヌース先生の本です。著者のライフワークであり初版は相当古い本ですがまだ未完だったと思います。昔、某情報工学の先生からクヌース先生だけは必ず敬称を付けておよびするとうかがったので、私もクヌース先生とお呼びすることにしています。大学に就職した後に、一応読んでおかないとモグリかなと思って訳書で読みました。ちなみに私が読んだのは旧訳の方です。 * 展示では、原著初版と邦訳(底本は第2版)を紹介します(一部、原著の第2版も所蔵しています)。 |
| The art of computer programming / D.E. Knuth (Addison-Wesley, c1968-1973) | 図書館オープン書庫(一般図書) 548/Kn8/1-3 |
|
| 理科系の作文技術 / 木下是雄著 (中央公論新社, 2002.6) | 図書館文庫・新書 407/Ki46 |
大学生の頃に読みました。タイトル通りに理系の文章をキチンと作るのに役立つ技術が書かれています。相当に昔の本なのですが、基本的考え方は今でも通用します。若いうちに読んでおくことをおすすめします。 |
| プログラムはなぜ動くのか : 知っておきたいプログラミングの基礎知識 / 矢沢久雄著. -- 第3版 (日経BP, 2021.5) | 図書館一般図書 548.964/Y67ni |
現代の情報社会で人が意識するしないに関わらず深く関わっているコンピューターやプログラム、その仕組みを知らずとも暮らしてはいけますが、現代人たるものその背景は常識として押さえておきたいものです。本書は、初版2001年と相当古いものですが版を重ねるごとに内容は大きく更新されており、現在は2021年第3版です。当時、あちこちの本屋に平積みされていたベストセラーです。 * 図書館では2版 (2007)も所蔵しています。 |
| 暗号技術入門 : 秘密の国のアリス / 結城浩著. -- 第3版 (SBクリエイティブ , 2015.9) | 図書館一般図書 548.93/Y97s |
現在の情報社会を支える現代の暗号技術について、平易に書かれています。初版はかなり古いですが版を重ねて加筆修正されており、現在は第3版です。現代暗号技術は数学基盤で支えており、多くの種類の暗号が組み立てられています。数学や情報科学を専門にしない人でも、本書の解説で暗号の常識を理解できるようになっています。 この著者は他にも多くのIT分野の本を出しており、文章が読みやすいのでおすすめです。 |
展示の様子


浅本先生(2022/12/12)
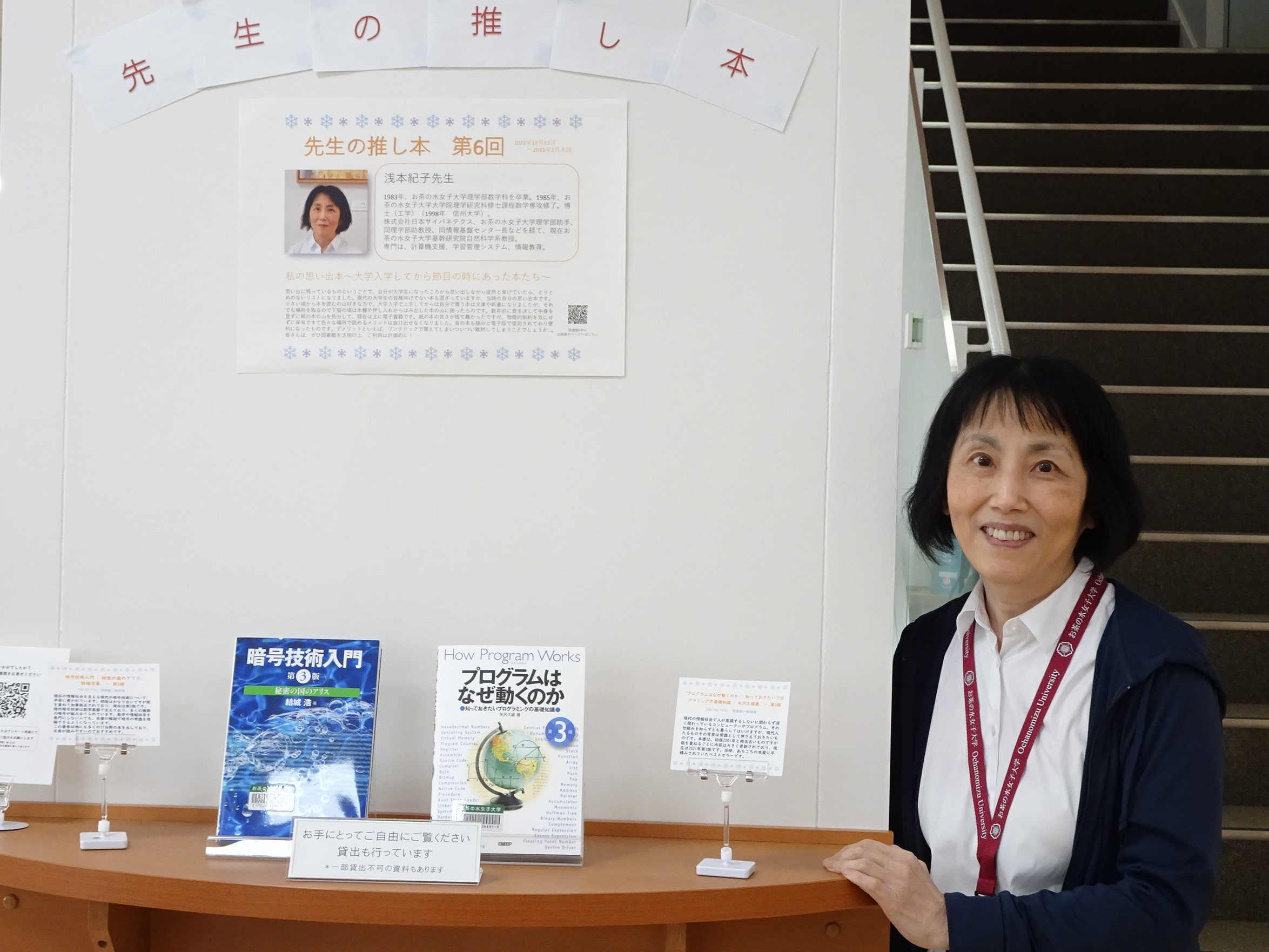
[ポスターは
こちら]
第7回は赤松利恵先生です。
過去のシリーズ企画展示
第1回 加藤美砂子先生 乱読のススメ
第2回 三浦徹先生 発見と行動
第3回 小谷眞男先生 わたしを ・ なした ・ 本たち(とカルタ)
第4回 松島のり子先生 原点――そこから、それから。
第5回 難波知子先生 読書嫌いの私が出会った本 〈小さいおうち〉から〈青春の終わり〉・〈お別れの始まり〉まで
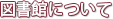




 企画展示一覧はこちら
企画展示一覧はこちら