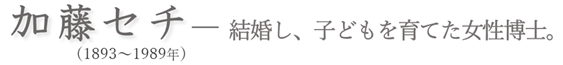
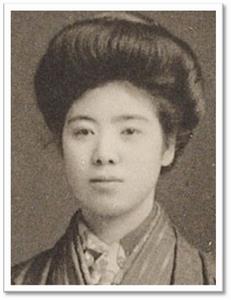 加藤セチは、自然科学の分野、特に吸収スペクトルによる化学の研究に貢献した研究者で、保井コノ、黒田チカにつぐ、日本で3番目の女性理学博士です。
加藤セチは、自然科学の分野、特に吸収スペクトルによる化学の研究に貢献した研究者で、保井コノ、黒田チカにつぐ、日本で3番目の女性理学博士です。
加藤は、明治26(1893)年に山形県東田川郡押切村(現、三川町)に生まれました。加藤家は、押切村の大地主でしたが大型酪農経営が父の代で失敗、さらに明治27年の庄内地震では母、兄、姉が家屋の下敷きになって焼死する惨事に見舞われます。父は、再婚をし再起を図りますが、上手くいかず明治41年に病死します。
鶴岡高等女学校(現、県立致道館中学校・高等学校)に在学していた加藤は、家計を支えるために教師になることを決意し、退学して山形女子師範学校(現、山形大学地域教育文化学部)に入学し直しました。明治44年3月に同校を首席で卒業、庄内の狩川小学校に奉職しますが、継母の勧めもあり、上京、大正3(1914)年に東京女子高等師範学校理科に入学します。大正7年に優秀な成績で卒業すると、札幌の北星高等女学校(現、北星学園女子中学高等学校)に赴任します。その年の夏、加藤は母校女高師の生徒と共に北海道帝国大学を見学し、そこで総長から、現在女子学生は一人もいないが門戸を閉ざしているわけではない、と聞き早速願書を大学に提出します。ところが、総長の意に反して、大学内では反対意見が多かったため、加藤は総長室前で座り込みまでおこないます。結果、正規の学生と認められませんでしたが、正規学生と同様に講義と研究指導を受けられる全科選科生としての入学を勝ち取りました。北大初めての女子学生でした。加藤は、高等女学校の教師を続けながら3年で全選科25科目を修了、修了論文「The Effect of Dry Condition upon the Germination of Apple Seeds.(林檎の種子発芽に対する乾燥の影響)」 が評価され農芸化学科の副手となり、北星高等女学校を退職しました。
1年後の大正11年、東京駒込の理化学研究所(以下、理研)で女性初の研究生となりますが、その間に建築家で同郷の佐藤得三郎と結婚、理研に入所した月に長男を、その2年後に長女を出産しています。
理研では、分光学を学び、吸収スペクトルを利用した化合物の分析に取り組み、昭和6(1931)年、主論文「アセチレンの重合」のほかに12編の副論文を添えて京都帝国大学に提出し、理学博士の学位を受けることができました。
その後も研究を続け、昭和17年には理研の研究員となり、昭和28年には女性初の主任研究員となりました。昭和30年の定年退職後も嘱託として理研に残り研究を続けますが、昭和35年に理研を退職します。その後は、相模女子大学、川村短期大学、上野学園大学などで教鞭を執ったほか、ボランティアで中・高の理科教員を対象とした「理科ゼミ」を主宰するなど後進の指導に当たりました。
略歴
| 明治26(1893)年 | 加藤正喬、妻みよの三女として、山形県東田川郡押切村(現三川町)に生まれる。 |
| 明治27(1894)年 | 10月22日、庄内地震発生。母みよ(25歳)、兄義彰(6歳)、姉志ん(5歳)が焼死。父正喬はその後、キンと再婚。 |
| 明治41(1908)年 | 3月、父正喬死去。教師になるために、鶴岡高等女学校を退学し、山形女子師範学校に入学し直す。 |
| 明治44(1911)年 | 山形女子師範卒業。庄内の狩川小学校に教師として勤務。 |
| 大正3(1914)年 | 4月、東京女子高等師範学校理科に入学。 |
| 大正7(1918)年 | 3月、東京女子高等師範学校理科卒業。(写真) 4月、札幌の北星高等女学校に教師として勤務。 9月、北海道帝国大学農科大学農学科第一部に全科選科生として入学、同大学の女子学生第一号となる |
| 大正8(1919)年 | 4月1日、北海道帝国大学農科大学は北海道帝国大学農学部と改称。 |
| 大正10(1921)年 | 3月、同大学農学部農学科修了。同時に北星高等女学校退職。 4月、同大学農学部農芸化学科の副手を嘱託される。 同年狩川村の佐藤得三郎と結婚し、加藤家の養子に迎える(28歳)。 |
| 大正11(1922)年 | 9月、東京の財団法人理化学研究所の研究生となり、分析化学の和田猪三郎研究室に配属。 9月21日、長男仁一出産。 |
| 大正13(1924)年 | 1月3日、長女コウ出産。 |
| 昭和6(1931)年 | 6月10日、京都帝国大学より理学博士の学位を授与。主論文題目「アセチレンの重合」、副論文12篇。 保井コノ、黒田チカに続く日本女性で3番目の理学博士、化学の分野では黒田に次いで2番目(38歳)。 |
| 昭和8(1933)年 | この年以降、京都帝国大学理学部で特別講義「分子の電子構造と化学反応」を行う。 |
| 昭和17(1943)年 | 9月、理化学研究所副研究員、12月に研究員となる。 |
| 昭和20(1945)年 | 長男仁一戦死。 |
| 昭和28(1953)年 | 理化学研究所主任研究員となる(女性初の主任研究員)。 |
| 昭和29(1954)年 | 定年退職(1960年まで理化学研究所特別研究室嘱託)。 |
| 昭和34(1959)年 | 夫得三郎死去。 |
| 昭和35(1960)年 | この年から15年間、現役の理科の高校教員を対象とした「理科ゼミ」を無料で主催。 |
| 昭和43(1968)年 | 6月1日、故郷の三川町の最初の名誉町民の称号を贈られる(74歳)。 |
| 平成元(1989)年 | 3月17日、東京の自宅の書斎で脳梗塞のため倒れ、直ちに入院したが回復せず、3月29日永眠。享年95歳。 5月15日、故郷山形県三川町の曹洞宗耕福寺の加藤家代々の墓に埋葬される。 |