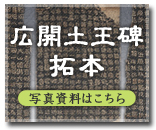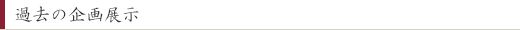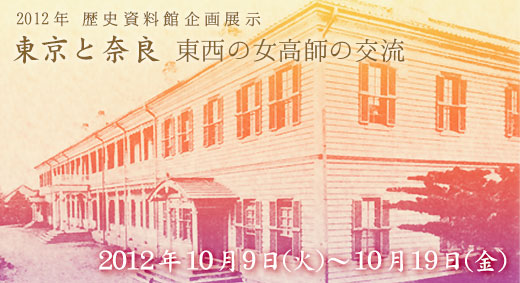
2012年企画展示「東京と奈良 東西の女高師の交流」
お茶の水女子大学の前身である東京女子高等師範学校と奈良女子大学の前身である奈良女子高等師範学校は、
明治41(1908)年の奈良女高師の創立以来、共に日本の女子教育の要であり、女子教員を養成するという同じ目的を持つ「姉妹校」として互いに交流していました。
例えば、毎年恒例の修学旅行では、東京女高師は奈良女高師を、奈良女高師は東京女高師を「交換訪問」し、親睦を深めていました。
そして、その交流は戦後の学制改革を経て、唯二つの国立女子大学となった現在も続いています。
今年は、奈良女高師の第1期生が東京女高師を修学旅行で初めて訪れた大正元年(1912)年から100年目の記念の年にあたります。
この機会に写真パネル約50点を中心に、当時の資料を交えて両校の交流の歴史を紹介します。
開催時の案内はこちら ⇒ 2012年企画展示
東西の女高師の創立
 明治8(1875)年、女子の教員養成を目的として東京女子師範学校がお茶の水の地(現:文京区湯島)に開校しました。
後に女子高等師範学校となり、女子の最高学府として、覇気に富む女性たちの憧れの的となりました。
明治41(1908)年、第二の女高師として奈良女子高等師範学校が創立し、女子高等師範学校は東京女子高等師範学校と改称しました。
二つの女高師は校風の違いもありましたが、同じ目的を持つ学校として互いを意識しながら連携と交流をしていました。
現在も 残る創立当時の校舎や生徒の写真により、両校の創立当時の様子を偲ぶことができます。
明治8(1875)年、女子の教員養成を目的として東京女子師範学校がお茶の水の地(現:文京区湯島)に開校しました。
後に女子高等師範学校となり、女子の最高学府として、覇気に富む女性たちの憧れの的となりました。
明治41(1908)年、第二の女高師として奈良女子高等師範学校が創立し、女子高等師範学校は東京女子高等師範学校と改称しました。
二つの女高師は校風の違いもありましたが、同じ目的を持つ学校として互いを意識しながら連携と交流をしていました。
現在も 残る創立当時の校舎や生徒の写真により、両校の創立当時の様子を偲ぶことができます。
修学旅行を通じた交流
 東京女高師は明治43(1910)年に4年生が関西方面修学旅行を行い、初めて奈良女高師を訪ねています。
そして、奈良女高師では第1期生が4年生になった大正元(1912)年に東京方面修学旅行を行い、初めて東京女高師を訪問しています。
後に、春には東京から奈良へ、秋には奈良から東京へ「交換訪問」するのが恒例となりました。
奈良女子大学には女高師時代の修学旅行に関する書類群が遺されており、生徒同士が睦まじく交流した歓迎会の様子や、東京女高師の校舎に対する生徒の感想がそこには記されています。
東京女高師は明治43(1910)年に4年生が関西方面修学旅行を行い、初めて奈良女高師を訪ねています。
そして、奈良女高師では第1期生が4年生になった大正元(1912)年に東京方面修学旅行を行い、初めて東京女高師を訪問しています。
後に、春には東京から奈良へ、秋には奈良から東京へ「交換訪問」するのが恒例となりました。
奈良女子大学には女高師時代の修学旅行に関する書類群が遺されており、生徒同士が睦まじく交流した歓迎会の様子や、東京女高師の校舎に対する生徒の感想がそこには記されています。
関連リンク
唯二つの国立女子大学の誕生
 大正期後半から昭和初期にかけて、両女高師は大学昇格のための運動を全学あげて展開しました。
そこでは、特に両校の同窓会組織である桜蔭会と佐保会が連携して活発に行動をしています。
この大学昇格への切なる願いは戦後の学制改革に引き継がれ、両校は国立女子大学への昇格を目指すこととなりました。
実現に向けては幾多の困難もありましたが、学校関係者の多大な努力が実 り、女高師の歴史と実績が認められ、昭和24(1949)年、新制の国立女子大学として発足しました。
大正期後半から昭和初期にかけて、両女高師は大学昇格のための運動を全学あげて展開しました。
そこでは、特に両校の同窓会組織である桜蔭会と佐保会が連携して活発に行動をしています。
この大学昇格への切なる願いは戦後の学制改革に引き継がれ、両校は国立女子大学への昇格を目指すこととなりました。
実現に向けては幾多の困難もありましたが、学校関係者の多大な努力が実 り、女高師の歴史と実績が認められ、昭和24(1949)年、新制の国立女子大学として発足しました。
現在も続く交流
戦後に新制大学として発足したお茶の水女子大学と奈良女子大学は、現在においても、単位互換等の協定を締結し、大学間の交流が行われています。 また、両大学間の体育会系のクラブでは交流試合が毎年行われるなど、学生間の交流も続けられています。 両大学に今も残る女高師時代に竣工した校舎は、近年、日本の女子教育の歴史を物語る建築物として国の登録有形文化財に指定されました。 両大学は女高師時代から百年を超える歴史と伝統を生かし、女性の高等教育機関として常により高度な学術研究と教育を目指しさらなる発展を続けています。
初の女子学生の帝国大学入学と女高師

 大正2(1913)年、東北帝国大学へ三人の女子学生が初めて入学しました。
それまで帝国大学では女子の入学資格は認められておらず、画期的なことでした。
入学したのは東京女高師卒業の黒田チカと牧 田らく、そして日本女子大学校卒業の丹下うめでした。
このことに刺激を受けた奈良女高師の野尻精一校長は、東北帝国大学の北条時敬総長へ参考として入学試験問題を送ってほしいと手紙で依頼しています。
(写真左 黒田チカ、右 牧田らく)
大正2(1913)年、東北帝国大学へ三人の女子学生が初めて入学しました。
それまで帝国大学では女子の入学資格は認められておらず、画期的なことでした。
入学したのは東京女高師卒業の黒田チカと牧 田らく、そして日本女子大学校卒業の丹下うめでした。
このことに刺激を受けた奈良女高師の野尻精一校長は、東北帝国大学の北条時敬総長へ参考として入学試験問題を送ってほしいと手紙で依頼しています。
(写真左 黒田チカ、右 牧田らく)
桜蔭会と佐保会―両女高師の同窓会
 東京女高師・お茶の水女子大学の同窓会である桜蔭会は明治37(1904)年に、奈良女高師・奈良女子大学の同窓会である佐保会は大正3(1914)年3月に発会しました。
特に、卒業後は教員となるとい う共通の目的があった女高師時代においては、両会が積極的に交流し連携した活動を行いました。
両会は女子の最高学府の同窓会としての誇りを持ち、母校の発展のため、さらには広く社会に貢献する活動を現在においても続けています。
(写真 大正初期の桜蔭会事務所)
東京女高師・お茶の水女子大学の同窓会である桜蔭会は明治37(1904)年に、奈良女高師・奈良女子大学の同窓会である佐保会は大正3(1914)年3月に発会しました。
特に、卒業後は教員となるとい う共通の目的があった女高師時代においては、両会が積極的に交流し連携した活動を行いました。
両会は女子の最高学府の同窓会としての誇りを持ち、母校の発展のため、さらには広く社会に貢献する活動を現在においても続けています。
(写真 大正初期の桜蔭会事務所)
広島女子高等師範学校―もう一つの女高師
広島女子高等師範学校は、昭和20(1945)年に、第三の女高師として広島市に創立しました。 戦時下の緊迫した状況の中、財団法人山中高等女学校からの校地、校舎、設備等の寄付により実現した創立でした。 開校まもない8月6日に原子爆弾が投下され、爆心地より1.7kmの地にあった広島女高師は甚大な被害を受けました。 第二次世界大戦後は広島大学へ包括され、教育課程の一部は教育学部に継承されました。